育児介護休業法をわかりやすく解説!2025年改正の理由と対応策
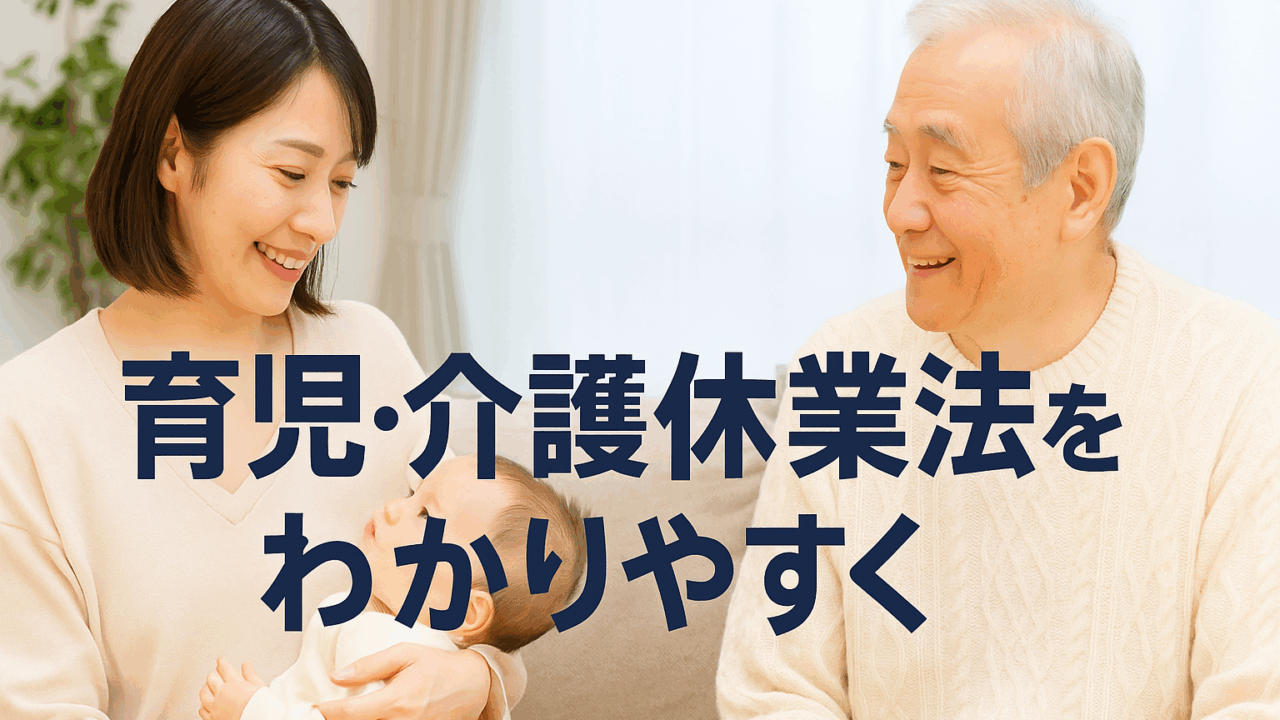
育児や介護をしながら働く方にとって、仕事との両立は大きな課題です。そうした状況に対応するために定められているのが、育児介護休業法です。この法律には、育児休業や介護休業、子の看護休暇、介護休暇といった制度があり、それぞれ対象や条件が異なります。
2025年には改正が行われ、残業免除の対象拡大やテレワークの努力義務化、育休取得状況の公表義務など、企業が対応すべき内容も増えました。また、短時間勤務制度や労働時間の制限といった働き方に関する柔軟な対応も求められています。
この記事では、育児介護休業法をわかりやすく整理し、必要な制度や改正ポイント、企業としての対応策について簡潔にご紹介します。
育児休業・介護休業など各制度の対象者と取得条件を理解できる
2025年の法改正内容と企業に求められる対応が分かる
短時間勤務やテレワークなど柔軟な働き方の制度を把握できる
育休取得状況の公表義務や残業免除の拡大ポイントを理解できる
育児介護休業法をわかりやすく解説します
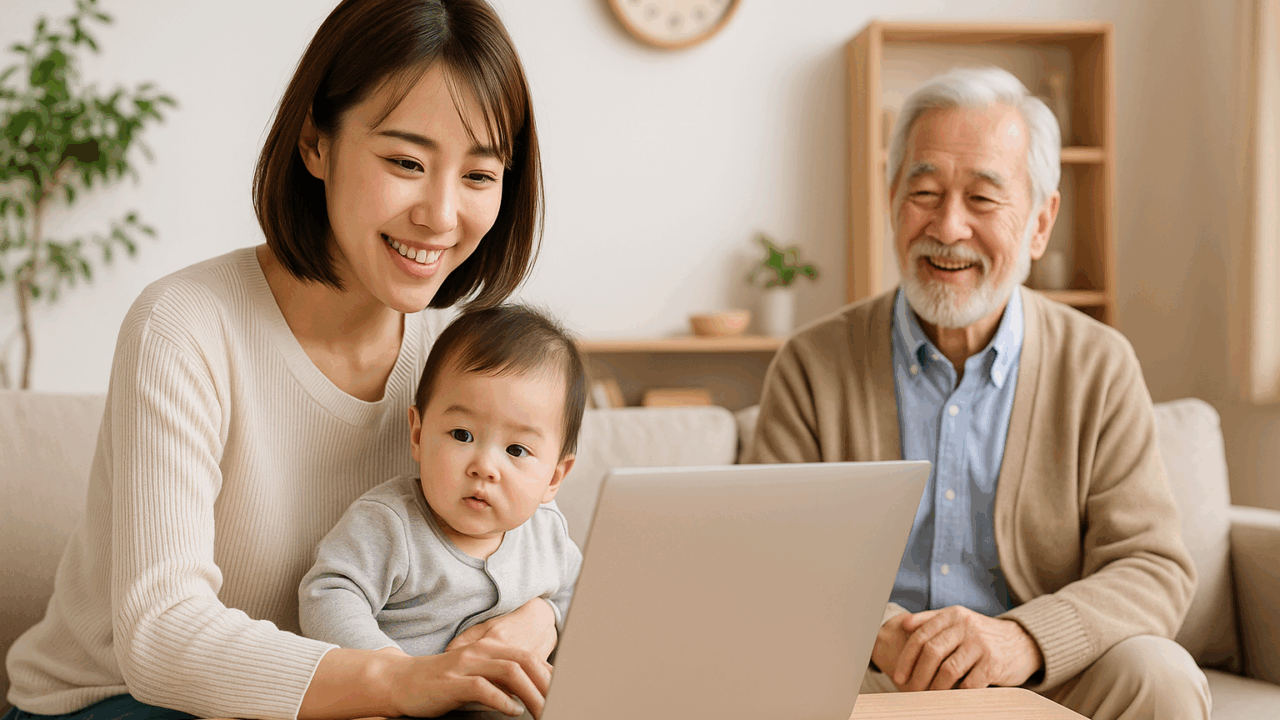
育児休業の対象者と取得条件
育児休業は、原則として1歳未満の子どもを養育する従業員が取得できる制度です。正社員だけでなく、一定の条件を満たせば契約社員やパートタイム労働者でも利用可能です。
なぜなら、働き方に関係なく、子育てと仕事の両立を支援することがこの制度の目的だからです。例えば、雇用期間が1年以上続いており、子が1歳6ヶ月になるまでに契約が終了しない見込みであれば、育児休業を取得できる可能性があります。
ただし、日雇い労働者や雇用期間が極端に短い場合などは対象外となる点に注意が必要です。また、労使協定によって一部の従業員が除外される場合もあります。申請にあたっては、自社の就業規則を確認した上で、上司や人事担当者と事前に相談しておくと安心です
介護休業の対象者と取得条件
介護休業は、家族が継続的な介護を必要とする場合に取得できる制度です。具体的には、2週間以上の「常時介護」が必要な状態であることが条件となります。
この制度が設けられた背景には、仕事と介護の両立を可能にすることで離職を防ぐという目的があります。対象となる家族は、配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫など、法律で定められた範囲に限られています。
休業は対象家族1人につき通算93日まで、3回に分けて取得できます。ただし、契約社員であっても、93日を超える期間に契約満了が確定している場合は対象外となります。企業によっては詳細な条件や申請方法が異なるため、事前に確認することが大切です
子の看護休暇とは?対象と日数
子の看護休暇とは、小学校3年生までの子どもが病気やケガなどで世話を必要とする際に取得できる休暇制度です。健康診断や予防接種の付き添いも対象になります。
この制度の特徴は、年次有給休暇とは別枠で休暇が取得できる点にあります。たとえば、子どもが1人の場合は年に5日、2人以上なら年10日まで取得可能です。勤務形態にかかわらず対象になる場合が多いですが、週の労働日数が2日以下の方などは、労使協定によって除外されることもあります。
注意点として、日雇い労働者は対象外であること、また事前に会社の規定や申請方法を確認する必要がある点が挙げられます。急な体調不良や感染症流行時など、家庭と仕事の両立を支える大切な制度です
介護休暇の内容と利用のしかた
介護休暇は、家族の介護や通院の付き添いなど、一時的なサポートが必要な日に取得できる制度です。育児休業や介護休業と異なり、短期間で利用できる点が特徴です。
利用できる日数は、介護対象の家族が1人であれば年5日、2人以上なら年10日が上限となっています。また、1日単位だけでなく時間単位での取得も可能です。この柔軟性が、日々の介護と仕事を両立させる上で非常に役立ちます。
ただし、取得にあたっては事前申請が必要で、会社によっては取得ルールが異なることもあります。また、日雇い労働者や週の所定労働日数が少ない方は除外される場合があるため、注意が必要です。あらかじめ社内制度を確認しておくことがスムーズな利用につながります
短時間勤務制度の基本ルール
短時間勤務制度とは、子育てや介護をしている従業員が、1日の労働時間を短縮して働ける制度です。育児の場合は、原則として子どもが3歳になるまで利用できます。
この制度は、フルタイム勤務が難しい状況でも働き続けられるように設けられています。例えば、通常8時間の勤務を6時間に短縮するといった働き方が可能です。企業によっては5時間45分などの細かい設定もあります。
ただし、日雇い労働者や所定労働時間が6時間以下の方など、一部の従業員は対象外となります。また、制度の導入が難しい業種では、代替措置としてテレワークなどが提案されることもあります。職場ごとの就業規則をしっかり確認しましょう
労働時間の制限制度について
育児や介護を理由に、一定の条件を満たす従業員は所定外労働(残業)や深夜業務の免除を申請できます。これは、家族のケアをしながら無理なく働くための支援制度です。
この制度は、労働者が希望すれば原則として企業は対応しなければなりません。例えば、未就学児を育てる従業員が残業の免除を申し出ると、それに応じた対応が必要となります。深夜勤務についても同様で、介護の必要がある場合などには免除を受けることができます。
ただし、雇用期間が1年未満の場合や日雇い労働者、週2日以下の勤務者は対象外となる点に留意しましょう。制度の申請には手続きが必要なため、前もって人事担当者と相談しておくとスムーズです
育児介護休業法をわかりやすく理解する改正内容

2025年4月からの主な改正ポイント
2025年4月の改正では、育児や介護と仕事を両立しやすくするために、複数の制度が見直されました。中でも注目されるのが、残業免除の対象拡大や、テレワーク導入の努力義務化です。
これにより、小学校入学前の子どもを養育する社員が、より柔軟に働けるようになりました。例えば、以前は3歳未満の子どもに限定されていた残業免除の対象が、未就学児まで広がったのです。また、介護をしている社員に対してもテレワークの選択肢を持たせることが企業に求められます。
一方で、制度導入に向けた社内調整が課題になる企業もあるでしょう。業種や業務内容によってはテレワークが困難な場合もあります。改正内容を正確に理解し、自社の体制と照らし合わせて準備を進めることが大切です
2025年10月からの義務化対応とは
2025年10月からは、3歳から小学校就学前の子どもを育てる従業員を対象に、柔軟な働き方を支援する措置が義務化されます。これは、育児による離職を防ぐための新たな取り組みです。
具体的には、始業時刻の変更、テレワーク、保育施設の設置、短時間勤務など、5つの選択肢のうち2つ以上を企業が用意する必要があります。従業員はその中から1つを選んで利用することができます。
ただし、制度の整備や運用には一定のコストや労力がかかります。業務体制の見直しや人員調整が必要になる場合もあるため、早めの対応が求められます。従業員への個別周知と意向確認も義務となるため、制度導入の際にはコミュニケーションが鍵となります
残業免除対象の拡大ポイント
育児・介護休業法の改正により、残業免除の対象者が拡大されました。従来は3歳未満の子どもを育てる社員のみが対象でしたが、改正後は小学校入学前までの子どもを持つ社員も対象となります。
この変更は、子育てと仕事の両立を支援するうえで大きな一歩です。実際に保育園や幼稚園の行事、急な体調不良などで早退が必要になることは珍しくありません。残業を免除することで、親としての役割を果たしやすくなります。
一方で、職場内での業務分担や人手不足が課題になる可能性もあります。制度の趣旨を共有し、チーム全体での協力体制を整えることが、スムーズな運用につながります
テレワークの努力義務化とは
2025年4月から、育児や介護を行う従業員へのテレワーク導入が企業の「努力義務」とされました。これは、家庭の事情により通勤や通常勤務が難しい従業員を支援するための措置です。
対象となるのは、3歳未満の子どもを育てる社員や、要介護状態の家族をケアする社員です。テレワークが可能であれば、仕事と家庭の両立がしやすくなり、離職防止にもつながります。
ただし、業務内容によっては在宅勤務が難しい職種もあります。そのような場合は、代替手段として始業時刻の変更や短時間勤務制度を活用するなど、柔軟な対応が求められます。努力義務とはいえ、積極的な導入が企業の信頼にも直結します
育休取得状況の公表義務とは
改正法により、従業員数が300人を超える企業にも、男性の育児休業取得状況の公表が義務づけられました。これは、育休を取りやすい職場づくりを促進する目的があります。
これまでは1,000人超の企業のみが対象でしたが、対象範囲が広がることで、多くの企業に透明性が求められるようになります。公表内容は、インターネットなどで一般の人が閲覧できる形での発信が必要です。
とはいえ、正確なデータ収集や集計方法の整備が必要となり、事務作業の負担が増えるケースもあるでしょう。しかし、企業の育児支援への取り組みを可視化することで、採用活動や社内定着率にも好影響を与えると期待されています
企業に求められる準備と対応策
育児・介護休業法の改正を受けて、企業には複数の準備が求められています。まず取り組むべきは、就業規則の見直しと制度内容の社内周知です。
法改正によって制度が変わるたびに、対応が後手に回ってしまう企業もあります。これを防ぐには、厚生労働省などの公的情報を常に確認し、自社の制度と照らし合わせてアップデートしていく姿勢が重要です。
さらに、各種申請書や届け出のフォーマットを整備することも効果的です。社員が必要な手続きをスムーズに進められることで、制度利用への心理的ハードルを下げることができます。制度の「存在」だけでなく「活用しやすさ」も企業の対応力の一部といえるでしょう

育児休業は1歳未満の子どもを育てる労働者が取得できる
介護休業は対象家族ごとに通算93日まで取得可能
子の看護休暇は小学校3年生修了までの子どもが対象となる
介護休暇は1日や時間単位で柔軟に取得できる
短時間勤務制度は育児や介護を支える労働時間短縮の仕組み
労働時間の制限制度により残業や深夜業務の免除が可能になる
2025年4月から残業免除の対象が未就学児育児者まで拡大された
テレワーク導入が育児・介護の場面で努力義務化された
子の看護等休暇の対象年齢や取得理由が広がった
男性の育児休業取得状況の公表義務が企業に課される
柔軟な働き方を支援する措置が2025年10月から義務化される
育児と仕事の両立に関する意向聴取と配慮が企業に求められる
就業規則の整備は法改正対応の基本的な準備となる
各種申請書類のフォーマット整備が制度利用を促進する
制度の理解と活用が離職防止や職場の信頼構築につながる













